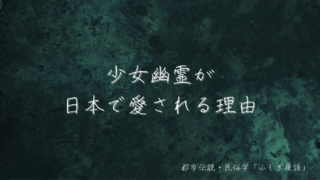 花子さん
花子さん 子どもが怪異を“少女”として認識する心理学
子どもは曖昧な気配や影を“少女の姿”として認識しやすい傾向があります。その心理的背景には、ジェンダー認知、親しみやすさ、社会的学習が影響しています。花子さんが少女像で定着した理由を徹底解説します。
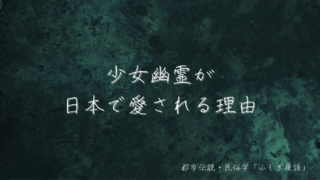 花子さん
花子さん 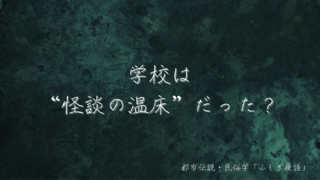 花子さん
花子さん 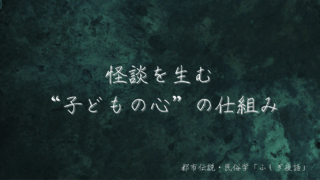 花子さん
花子さん 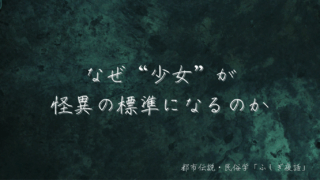 花子さん
花子さん 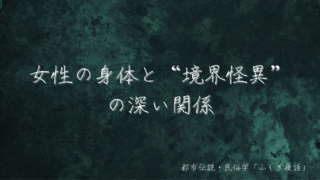 花子さん
花子さん  花子さん
花子さん 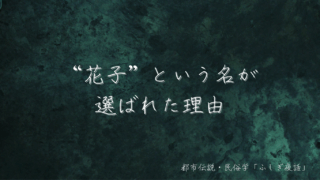 花子さん
花子さん 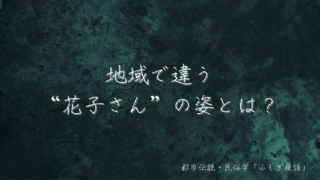 花子さん
花子さん  花子さん
花子さん 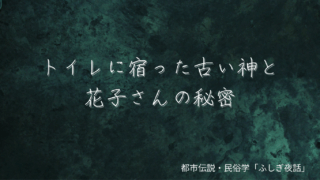 花子さん
花子さん